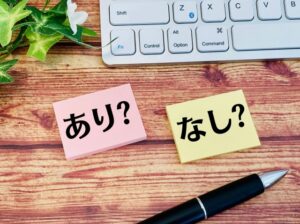進捗どうですかって聞いたら『順調です!』って言ってたのに、全然手つかずだったんです…



あるあるですね。『順調』って言葉、実は日本とベトナムで意味が違うんです。



そうなんですね…。たしかに表情では自信ありそうだったけど…。



いわゆる“報告文化の違い”ですね。でもちゃんと対策すれば防げますよ
はじめに
ベトナムのオフショア開発でありがちなのが「順調です」という報告を信じていたのに、実際には全然進んでいなかったという“進捗報告ギャップ”。これは文化的背景や報告スタイルの違いが原因で起こることが多く、気づいたときには手遅れになっていることも。本記事では、その原因と、進捗を正確に把握するための具体的な対策を解説します。
「順調です」の裏にある曖昧な進捗報告文化
ベトナムでは「Yes」と言っても「本当に理解している」とは限らず、また否定的な表現を避ける文化が根付いています。そのため、作業が遅れていても「順調です」と答えることで波風を立てないようにする傾向があります。
筆者はあいまいな表現を避けようと進捗を%で報告してもらっていましたが、正直あまり効果はありませんでした。あまり細かく定義しても無意味だと思い0%を「未着手」、50%を「作業中」、100%を「完了」と定義しましたが、そもそも完了の定義が違うので意味がなかったように思います。
また、日本人が「順調=予定通りに進んでいる」と受け取るのに対し、ベトナムでは「大きな問題はない(=特に報告することもない)」というニュアンスで使われる場合もあります。そもそも特に報告することもないという判断が間違っていることが殆どなのですが。
実例:「順調です」に騙された…納期直前の大混乱
筆者が実際に経験したケースでは、進捗確認のたびに「順調です」と返ってきていたタスクが、納期3日前に確認したところソースコードが未作成という事態が発生しました。ドキュメントの準備や要件の把握で止まっており、着手すらされていなかったのです。
別のケースでは、デザインの実装タスクにおいて「画面はほぼ完成しました」と報告されていたものの、実際には画面の骨組みだけが作成され、CSSは全く手がつけられていませんでした。チームは「HTMLがある=完成に近い」と認識しており、日本側の完成イメージとの乖離が大きく、納期後に大幅な修正が必要になりました。
さらにあるプロジェクトでは、「APIの連携は完了しています」と報告があったため結合テストを進めたところ、エンドポイントはつながっていたものの、エラーハンドリングやデータフォーマットの調整が一切されておらず、実質的に“未完了”であることが判明しました。
このような事態は、進捗の把握を“言葉”に頼っていると起きやすく、仕組みで防ぐ必要があります。
対策編:”順調です”を鵜呑みにしないための3つの確認ルール
対策1:進捗の定義を明確にする(WBS × タスク単位 × ステータスラベル)
進捗を曖昧な言葉ではなく「状態」で定義することが重要です。筆者自身、「順調」という言葉を信じてプロジェクトを進めていたところ、まったく作業が進んでいなかったという経験が何度もあります。そういったギャップを防ぐには、“どのフェーズにあるのか”を明確に定義し、タスクの進捗を可視化する必要があります。
タスク管理ツール(Jira、Backlog、Trelloなど)を使えば、作業の粒度を細かく設定でき、進捗状況を可視化しやすくなります。以下のようにステータスを分解し、「順調」といった抽象的な表現に頼らず、具体的な状況として管理しましょう。
- 未着手
- 着手済み
- 作業中
- レビュー待ち
- 修正中
- 完了
進捗はタスクベースで管理し、「順調」という曖昧な言葉を排除することがポイントです。
対策2:定例ミーティングで実物ベースで確認する
進捗確認ミーティングでは、口頭の報告だけでなく、実際の成果物や進行中のコードをスクリーンシェアで見せてもらうことが効果的です。筆者の経験では、報告上「進んでいる」とされていたタスクを画面共有で確認したところ、コードが雛形だけだったり、レイアウトが途中までしかできていないといったことが何度もありました。
エンジニアに悪気はなくても、感覚の違いから“やっているつもり”が“完了”と伝わってしまうのです。そうした食い違いを防ぐには、口頭だけでなく視覚的に進捗を確認することが何より重要です。
たとえば:
- 開発中の画面をFigmaやブラウザ上で共有
- コードをIDEでライブ表示して確認
- テスト結果やログのキャプチャを見せてもらう
この「実物主義」によって、報告と現実のギャップを最小化できます。
対策3:報告テンプレートを導入し、主観を排除
進捗報告に自由記述を使うと、報告の質にばらつきが出ます。あるチームメンバーは詳細に報告してくれる一方で、別のメンバーは「大丈夫です」の一言だけ、といった極端な差を何度も経験しました。こうした状況では、進捗の本当の状況を読み取るのが難しくなり、後手に回ることが多くなってしまいます。
それを防ぐには、進捗報告のフォーマットをテンプレート化して、誰が報告しても同じ項目を網羅するようにすることが効果的です。報告内容を定型化することで、主観を排除し、管理者側も比較・把握しやすくなります。以下の項目を固定化しておくと、進捗の見える化と早期の課題発見につながります。
- 現在のステータス(選択式)
- 完了した作業内容(箇条書き)
- 残作業とブロッカー
- 次回の予定
SlackやNotion、Googleスプレッドシートなどでテンプレートを回すことで、定量的・定型的な報告に変えることができます。
「順調です」という言葉には、国ごと・文化ごとに異なる意味が含まれていることがあります。
ベトナム側が「問題ありません」と伝えてきたにもかかわらず、あとで確認したら作業は手つかずだった、というケースが何度もありました。
これは、相手が意図的に嘘をついているわけではなく、「進んでいないこと」をネガティブに報告したくない、という文化的背景や人間関係への配慮が働いていることが多いのです。
だからこそ、進捗確認では曖昧な言葉を使わず、「今どの状態にあるのか」を具体的に示すことが重要です。そのためには、ステータスの定義を明確にし、成果物を視覚的に確認し、報告フォーマットも整備することで、“主観”ではなく“事実”で会話できる環境を整える必要があります。こうした仕組み化が、ベトナムとの信頼関係を築きながらも、正確なマネジメントを実現する鍵になると考えています。
筆者の経験上、進捗を“信じる”よりも“見える化する”姿勢が、プロジェクトの成功を左右する最大の鍵になります。
Skilligenceは、現場で成果を出すための研修・顧問・教材を提供する実務支援ブランドです。
・研修:要件定義・業務設計・LLM活用などを体系的に学べる実践講座
・顧問:プロジェクト進行や開発体制の課題を継続的にサポート
・教材:独学でも現場スキルを身につけられる学習コンテンツ
実務で使える知識と仕組みづくりを、学びから伴走まで一貫して支援しています。
▶ IT顧問サービスを見る
▶ 研修一覧を見る
▶ 教材一覧を見る(Starter・Advanced公開中)