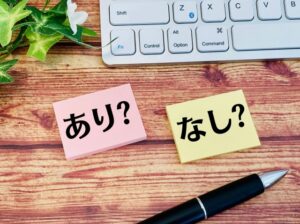レビューは毎回やってるはずなんですが、なんでこんなにバグが多いんでしょうか…



レビューって“やること”自体が目的になってないでしょうか?内容まで見てなかったら、それは形骸化してるってことかもしれないですね。



たしかに、細かい書き方の指摘はしてるけど、ロジックまではあまり見てないかも…



レビューの“中身”を見直すだけで、品質は一気に改善しますよ。
はじめに
「レビューはちゃんとしているのに、なぜかバグが減らない」――ベトナムとのオフショア開発において、こうした声は少なくありません。形式的なコードレビューが形骸化してしまい、本来の目的である品質向上を果たしていないケースが多々見られます。
本記事では、コードレビューが機能しない原因とその改善策について、実際の現場経験に基づきながら3つの具体的なポイントに絞って解説します。
形骸化したレビューとは?
レビューが「やったこと」に満足してしまっている状態、それが“形骸化”です。以下のような状況は要注意です。
- 表面的な指摘(インデントや変数名)だけで終わっている
- レビュワーがコードの理解を深めようとしていない
- 指摘内容が実装者に正しく伝わらず、修正されていない
実際、筆者の経験でも「レビュー済み」のPR(プルリクエスト)に重大なロジックミスが残っていたことがあり、確認するとレビューコメントはすべて「命名を変えてください」などの表層的な内容に偏っていたということがありました。
実例:レビュー済みなのに重大バグが混入したケース
あるAPI開発プロジェクトでは、エラーハンドリングが一切実装されていないコードがレビュー済としてマージされ、テスト環境でサーバーエラーを連発しました。レビュワーに確認すると「try-catchが入ってなかったのは気づいてたが、そこは仕様かと思った」との回答。こうした“憶測レビュー”はプロジェクトにとって極めて危険です。レビューは「確認と合意のプロセス」であり、「たぶん」「きっと」という曖昧な判断は排除すべきものです。
また、別のケースでは、パフォーマンスに重大な影響を与える無限ループが紛れ込んでいたにもかかわらず、レビュワーがコード全体を読まず、差分の一部だけを斜め読みして承認してしまっていました。これは、「時間がないからとりあえず承認しておこう」という心理が働いた典型例であり、レビュー文化が形だけのものになっていたことを象徴しています。このような経験を経て実感するのは、レビューには「明確な観点」と「形式ではなく実質を重視する文化」が不可欠だということです。チェックする側・される側双方の意識と仕組みの両方を整えることで、ようやくレビューが本来の力を発揮できるようになります。
レビューを「形」から「効果あるプロセス」に変える3つの改善策
対策1:レビュー観点の明文化(レビューガイドライン)
レビューが属人的にならないよう、観点を明文化するのが第一歩です。
レビューという行為は、単なる確認作業ではなく、品質と認識のズレを事前に検知するための重要な工程です。レビューを通じて「何を見ているのか」が明文化されていなければ、レビュー内容にばらつきが出て、期待される効果を得ることは難しくなります。
観点が人によって異なれば、品質の判断軸もぶれてしまい、信頼できるレビューになりません。
たとえば、以下のような観点は、どのレビューでも最低限確認すべきポイントとして明文化しておくとよいでしょう。特に経験が浅いレビュワーでも、こうした観点があれば何を見ればいいかが明確になりますし、見落としを減らすことにもつながります。
- 仕様通りに実装されているか
- ロジックは正しいか(境界値、例外)
- エラー処理や例外対応ができているか
- セキュリティ上の懸念はないか
- 可読性、保守性に問題はないか
プロジェクトやフェーズごとに観点をリスト化し、チェックリストとしてプルリクエストごとに確認を行う仕組みを作ると、レビューの質が安定します。
対策2:ペアレビュー・モブレビューの活用
レビュワーが一人だけだと、どうしても主観が強くなりがちで、意図しない見落としが発生することがあります。特に、自分と異なる視点からのフィードバックが得られないため、レビューの質が個人のスキルや判断力に依存してしまいがちです。そのような状況を改善する方法として有効なのが、ペアレビューやモブレビューといった複数人でのレビュー形式です。
こうしたレビュー手法を取り入れると、チェックの視野が広がり、レビュー時に発生する認識のズレや曖昧な仕様解釈も自然と議論されるようになります。また、レビュワーだけでなく実装者にとっても、設計意図や実装判断を説明する機会が生まれ、チーム内でのナレッジ共有や理解の促進にもつながります。
- ペアレビュー
- 開発者とレビュワーが1対1でリアルタイムに画面を共有しながらコードを確認します。実装意図や仕様の解釈についてその場で質問・確認ができるため、理解のズレや誤解を最小限に抑えることができます。特に新しい機能や複雑な処理に対しては、即時のコミュニケーションが有効に働きます。
- モブレビュー
- チームの複数人(3人以上)で1つのコードを一緒に読みながら意見を出し合い、その場で改善点を検討するスタイルです。視点の異なるメンバーが集まることで、ロジック、命名、設計、パフォーマンスといった多面的なレビューが可能となり、個人では見落としがちな問題点にも気付きやすくなります。教育効果やチームビルディングの観点からも非常に有効です。
対話を伴うレビューにすることで、コードの背景や意図が共有されやすくなり、チームの理解度と品質意識も高まります。
対策3:レビュー結果の記録と振り返りの仕組み化
レビューコメントが記録されず、修正されたかどうかも曖昧になっているプロジェクトは多いです。レビューというプロセスが本当に機能していたかどうかを後から検証する手段がなければ、問題が繰り返されるのは当然です。コメントがどのように扱われたのか、指摘が改善されたのか、それとも無視されたのか──そのプロセスを見える化し、蓄積していくことは、チーム全体の品質向上に直結します。
また、記録を残すことで、レビューの偏りや課題の傾向も見えるようになります。これは単なる履歴ではなく、次の改善に活かす“チームの資産”となります。特に多国籍チームにおいては、こうした客観的な記録が文化や言語の壁を越える重要な補助線にもなり得ます。
以下は、レビューコメントを記録・振り返ることで得られる具体的なメリットの一例です。こうした効果を意識することで、レビューという工程が「改善の起点」として機能するようになります。
- 指摘の傾向から、教育・育成ポイントが見える
- スプリント単位で振り返り、レビューの質自体を改善できる
- レビュワー間の観点のばらつきを是正できる
ある開発現場では、レビューコメントをスプレッドシートに残し、週1回の開発振り返りの中でレビュー自体をレビューするという仕組みを取り入れたところ、半年でバグ報告件数が40%以上減少したそうです。
ベトナムとのオフショア開発において、レビューが“形だけの儀式”になってしまうと、期待される品質担保の効果は得られません。レビューは本来、コードの品質だけでなく、チーム全体の理解度と設計思想を共有する場でもあります。
観点を明確にし、対話を増やし、仕組み化する。これらを地道に継続していくことで、レビューは単なる工程ではなく、プロジェクトを支える強力な品質基盤になります。
筆者自身、何度も失敗を経験したからこそ、レビューの“質”を高めることが、オフショア開発成功のカギであると強く感じています。
Skilligenceは、現場で成果を出すための研修・顧問・教材を提供する実務支援ブランドです。
・研修:要件定義・業務設計・LLM活用などを体系的に学べる実践講座
・顧問:プロジェクト進行や開発体制の課題を継続的にサポート
・教材:独学でも現場スキルを身につけられる学習コンテンツ
実務で使える知識と仕組みづくりを、学びから伴走まで一貫して支援しています。
▶ IT顧問サービスを見る
▶ 研修一覧を見る
▶ 教材一覧を見る(Starter・Advanced公開中)