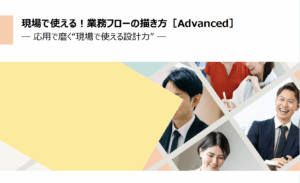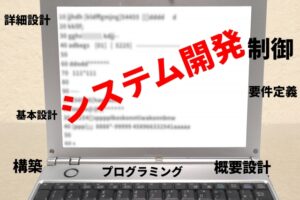オフショアって結局コストが安いから使われてるんですよね?



確かにそう思われがちですが、実際の現場を知ると“安さの神話”は崩れてきているんです。特にAIが台頭してからは状況が大きく変わっていますよ。
なぜオフショア開発は機能しなくなったのか
オフショア開発は2000年代以降、日本企業が人材不足と開発コスト高に悩む中で拡大しました。
特にベトナム、インド、インドネシアなどが人気拠点となり、「国内比で半分以下のコストで開発可能」と喧伝されました。
しかし実際には以下の課題が頻発しました。
- 品質のばらつき
- 進捗遅延や見積もり精度の低さ
- 言語・文化の壁によるコミュニケーション不全
結果として、日本側がレビュー・再実装・追加テストを重ねる必要があり、「安さ」どころか逆に高コスト化する事例が多発しました。
詳細解説:失敗パターン
- 技術力のばらつきによる品質低下
オフショア開発では、チーム内でスキル差が極端なことが多いです。例えば、フロントエンドの基本実装は問題なくても、非同期処理や権限周りになると一部のメンバーが対応できず、レビュー指摘が何十件も出てしまう。
結果、レビューや手直しに国内のシニア人材が時間を割き、「安いはずが日本側の人件費で逆転」という本末転倒が起こります。
現場でよくあるのは「見積では10日なのに、レビューと再実装で倍の工数がかかった」というパターンです。 - コミュニケーションの壁と文化ギャップ
英語や現地言語でやり取りしていると、相手が「Yes」と答えていても、実際は理解していないことが珍しくありません。仕様を説明して「わかりました」と返ってきても、数週間後に完成した成果物を見ると全く別物、という事態も。
文化的に「No」と言いにくい国では特にこの傾向が強く、誤解が発覚するのは後工程になります。
この齟齬が原因で設計変更や追加修正が頻発し、スケジュールの遅延や追加費用につながるのです。 - “テスト済み”でも本番で不具合が出る構造
典型的なのは「テスト済み」と報告されていても、本番環境に切り替えると障害が発生するケースです。
原因はほとんどの場合、DoD(完了の定義)の曖昧さにあります。例えば、検証環境ではデータ件数が1万件程度だったのに、本番では100万件あり、性能劣化が顕在化する。
あるいは、テストデータが固定化されていて境界値や時刻跨ぎ(例:日付変更や夏時間)のケースが抜けていた。
「やったつもり」のテストが量産され、結果的に本番で初めて重大な不具合が露呈するのです。 - 日本側がカバーして高コスト化
最も多いのは「結局、日本側が面倒を見る」パターンです。
ブリッジSEやPMが本来は管理に専念すべきなのに、レビューだけでは終わらず自ら手を動かして修正する。
結果、国内の高単価人材の工数がどんどん増え、**「オフショアに出したのに国内だけでやるより高くついた」**という皮肉な結果になります。
実際、筆者が経験したプロジェクトでも、海外側の実装40時間に対して、日本側のレビューと再実装で60時間以上かかり、コストが逆転しました。
転換点:AIの台頭
2023年以降、GitHub CopilotやChatGPT Code Interpreterなどの生成AIが普及しました。
単純な実装はAIの方が速く正確という時代が訪れています。
- CRUD処理やバリデーションはAIが即時生成
- コード品質はレビューを前提にすれば初級エンジニア以上
- テストケースや環境差分の検証補助もAIで可能
結果、「オフショアに頼むよりAI+シニア人材の方が効率的」という流れが強まっています。
解決策・実践ノウハウ
AI前提の開発プロセス設計
これからの開発では「まずAIにやらせる」が出発点になります。
たとえばCRUD処理やAPI呼び出しのサンプルコードは、AIに生成させた方が圧倒的に速い。
人間が担うのは「生成コードが要件に合っているか」「セキュリティや例外処理は十分か」をレビューする部分です。
AIを実装担当、エンジニアを設計と監査担当に分けることで、重複工数を減らせます。
少人数精鋭チームへのシフト
大規模なオフショアチームを動かすのではなく、シニアエンジニア、QA、PMの3〜5人程度のチームで回す形が有効です。
人数を絞ることで意思決定が速くなり、責任の所在も明確になります。
AIがカバーする部分を前提にするので、人員を大量投入する必要はなくなります。
グローバルチーム活用の新しい形
「人件費の安さ」で海外に頼るのではなく、専門領域を持つ海外エンジニアをピンポイントでアサインするのが現実的です。
例えば、デザインシステム構築に強い人材を週10時間だけリモートで参加させる、といったスタイル。
AIで大部分をまかないつつ、専門家を必要な時に投入するのがこれからのグローバル協働の姿です。
費用対効果の見直しポイント
オフショアでは「一人月単価」だけを見がちですが、これからは以下の観点で見直す必要があります。
- レビューや再実装にどれくらい国内の工数が割かれているか
- コミュニケーションにかかる時間と頻度(時差・言語差も含む)
- バグや手戻りでリリースがどれくらい遅れるか
単価が安くても、トータルで国内工数が増えていれば意味がありません。
AIと人材の最適な組み合わせ
具体的には次のように切り分けると効果的です。
- 画面設計やユーザー体験の設計:人間が担当
- 定型的な実装やテストコード:AIに任せる
- アーキテクチャ設計や品質基準の策定:シニアエンジニアが担う
こうすることで、人間の強みとAIの強みをそれぞれ最大化できます。
オフショア開発はかつて「コスト削減の切り札」でした。
しかし現場では「安さの神話」が崩れ、AIの台頭で過去の手法になりつつあります。
これからの鍵は「AI前提+少人数精鋭」の体制設計です。
Skilligenceは、現場で成果を出すための研修・顧問・教材を提供する実務支援ブランドです。
・研修:要件定義・業務設計・LLM活用などを体系的に学べる実践講座
・顧問:プロジェクト進行や開発体制の課題を継続的にサポート
・教材:独学でも現場スキルを身につけられる学習コンテンツ
実務で使える知識と仕組みづくりを、学びから伴走まで一貫して支援しています。
▶ IT顧問サービスを見る
▶ 研修一覧を見る
▶ 教材一覧を見る(Starter・Advanced公開中)