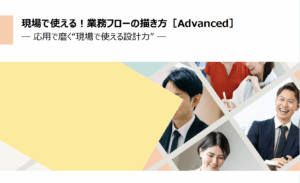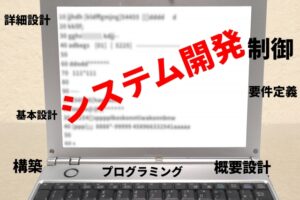最近ChatGPTって話題ですけど、要件定義の現場で使えるんですか?



もちろんです。ブレストやヒアリング準備、曖昧な要件の整理にもすごく役立つんです。うまく活用すれば、ミスも減らせますよ
Contents
ChatGPTを要件定義に活用するユースケース3選
ヒアリングの質問項目を自動生成
クライアント業種やシステム種別を入力するだけで、網羅的な質問リストを自動生成可能
プロンプト例:
- 「ネット通販サイトを新しく作り直すとき、どんなことをお客さんに聞けばいい?」
- 「今ある業務用のシステムを作り直すときに、事前に確認しておくべきことは何?」
ChatGPTにこのように話しかけると、自動的に聞くべき質問リストを提案してくれます
曖昧な要件の具体化を支援
あいまいな要件(例:”使いやすいUI”、”柔軟な検索”)を具体的に言語化する補助に
プロンプト例:
- 「“柔軟な検索”の具体例を3つ挙げて」
キーワードで検索できる、カテゴリで絞り込める、複数条件を組み合わせて探せる など。ChatGPTに質問すれば、こうした例を提案してくれます - 「“業務に支障が出ない程度にバッチ処理する”とは、どんな条件か?」
夜間や休日に処理を実行する、処理時間が数分以内で終わる、業務に関係ないデータから順に処理する など。
ChatGPTが整理して説明してくれます
要件定義書のたたき台作成
構成やテンプレートを指示すれば、ドキュメントの初期稿を短時間で作成可能
プロンプト例:
- 「業務システムの機能要件一覧をMarkdownで作成して」
機能要件とは、「どんな機能が必要か?」というリストのことです。例えば「商品を検索する」「カートに入れる」「注文履歴を見る」など。Markdownという形式で、シンプルな見た目のリストを作ってくれます - 「非機能要件のサンプルを提示して」
非機能要件とは、「機能以外の大事な条件」のことです。例えば「画面表示は3秒以内」「毎日夜12時にバックアップする」など。ChatGPTは、そういった例をいくつか挙げてくれます
ChatGPTで”できること”と”できないこと”
できること
- ヒアリング準備の効率化
- 曖昧な要件のブレイクダウン
- 定型資料や議事録の下書き生成
できないこと
- 完全な正確性は保証できない(事実確認は必須)
- クライアント固有の事情は推測できない
- 日本語特有の曖昧表現に対する判断はまだ不十分な場面も
実務での導入ポイント
- 使う場面を明確にする(“準備用”として割り切る)
- ChatGPTはとても便利なツールですが、要件定義のすべてを任せるのではなく、「資料を作る前のアイデア出し」や「たたき台の作成」といった“準備段階”に使うのがベストです。たとえば、ヒアリングの前に質問項目を考えたり、要件の方向性を整理したりする場面に向いています。
- 生成結果を鵜呑みにせず、必ず検証する
- ChatGPTはあくまでAIなので、時には事実と異なる内容や、不正確な表現を返すことがあります。出力された文章や内容は、必ず自分の目で確認・修正し、信頼できる情報に基づいて判断することが大切です。
- プロンプト(指示文)を洗練させることで精度が上がる
- 「どんな答えがほしいか」を具体的に伝えることで、より正確で実用的な回答が得られます。たとえば「質問リストを作って」だけでなく、「ネット通販の管理者に聞くべき質問を5つ」などと明確に指示することで、よりよい結果が得られます。
- セキュリティや情報漏洩対策の観点も考慮する(機密情報は入力しない)
- ChatGPTに送信した内容は外部に保存・学習される可能性があります。そのため、会社名・顧客名・内部資料などの機密情報は絶対に入力しないようにしましょう。扱う内容が業務に関わる場合は、利用ルールをあらかじめ整備しておくのがおすすめです。
まとめ
ChatGPTは、要件定義工程における「思考の補助ツール」として非常に強力です。特に新人SEや準備に時間を割けないPMにとって、作業の下支えになる存在です。
ただし、あくまでも“補助”という立ち位置を忘れず、人間の判断や確認を前提に活用していきましょう。
Skilligenceは、現場で成果を出すための研修・顧問・教材を提供する実務支援ブランドです。
・研修:要件定義・業務設計・LLM活用などを体系的に学べる実践講座
・顧問:プロジェクト進行や開発体制の課題を継続的にサポート
・教材:独学でも現場スキルを身につけられる学習コンテンツ
実務で使える知識と仕組みづくりを、学びから伴走まで一貫して支援しています。
▶ IT顧問サービスを見る
▶ 研修一覧を見る
▶ 教材一覧を見る(Starter・Advanced公開中)