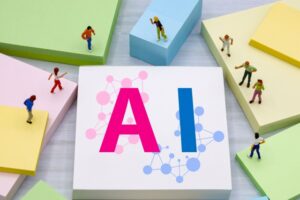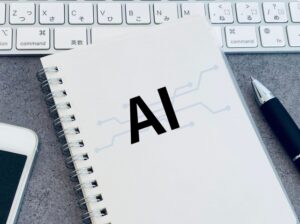最近LLMを使った開発案件が増えてきてますよね。でも正直、要件定義ってどうやればいいのかイメージが湧かなくて……。



そうですね。そこが一番つまずきやすいところなんです。従来の開発と同じ感覚で進めてしまうと、思わぬところで破綻してしまうんですよ。



やっぱり特有のポイントがあるんですね。



ええ、そうなんです。今日はその中でも特に押さえていただきたい5つのポイントを整理してみましょう。
なぜLLM開発では要件定義が難しいのか
従来のシステム開発では、要件定義は「入力がこうなら、出力はこう」という決定的なルールを明文化する作業でした。
しかしLLM開発では、従来のシステムのように「常に同じ入力なら同じ出力が返る」とは限りません。
同じ質問を繰り返しても微妙に表現が変わる、あるいはその場の文脈によって答えが揺らぐ、といった現象が当たり前に起こります。
さらに、正解が一つに定まらないケースも多いのが特徴です。
たとえば「良い要件定義の書き方は?」という質問に対して、A社なら「テンプレートを使う」と答えを求め、B社なら「顧客との合意形成を重視」と答えを期待するかもしれません。
どちらも間違いではなく、それぞれの文脈で「正解」になり得ます。
従来の開発では「要件=固定化された仕様」でしたが、LLMでは「要件=正解の幅をどう許容するか」を設計する必要があります。
この発想の転換ができないまま進めると、
- 「出力が安定しないからNG」
- 「期待した答えじゃないから不具合扱い」
といった議論に終始し、プロジェクトが迷走するのです。
よくある失敗例
- 「自然な文章で回答すること」とだけ記載 → 開発者ごとに解釈が割れ、レビューで「硬すぎる/砕けすぎる」と対立
- 「精度を高める」とだけ定義 → PoC段階で「どこまで行けば合格か」判断できず、無限に調整が続く
実務での工夫
- 曖昧な言葉は数値基準やサンプル出力に置き換える
- 要件定義書には出力例やテスト基準を必ず添付し、合意形成を支える
要件定義で迷走しないためのLLM開発5つのチェックポイント
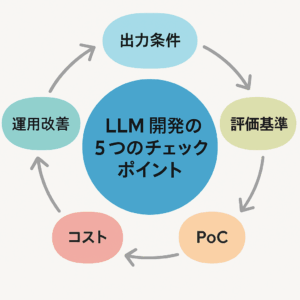
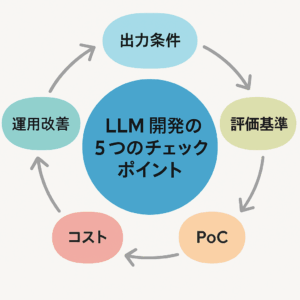
①出力条件を明確化する|曖昧な表現を避ける
LLMは「自然に」「丁寧に」といった曖昧な指示でも動きますが、これは現場では混乱のもとになります。
失敗例
- 「わかりやすく丁寧な文章」とだけ定義 → Aさんは敬語を徹底、Bさんはカジュアル寄り、と真逆の出力が発生
- テスト設計でも「わかりやすさ」が基準化できず、品質保証が進まない
実務での工夫
- フォーマットを固定する
例:「質問→回答→補足」の3段構成。誰が実行しても同じ形式になる。 - 禁止事項を明文化する
例:「スラング禁止」「必ずです・ます調」。暗黙知に頼らず明記する。 - サンプル出力を添付する
例:「発送はいつ?」→「○月○日に発送予定です。補足:発送完了後にメールでお知らせします。」
クライアントと「これが正解」と合意形成でき、レビュー・テスト基準としても活用できる。
👉 この3つをセットで実施すれば、「曖昧な要件」が「誰が読んでも同じ解釈になる仕様」に変わります。
②評価基準を数値で定義する|PoC段階の混乱を防ぐ
LLM開発で一番多いトラブルは「もっと精度を上げて」という曖昧な要求です。
これでは「どのくらいできれば合格か」が不明確で、プロジェクトが終わりません。
そこで大切なのが数値化です。数字で「合格ライン」を決めれば、誰が見ても同じ判断ができます。
1.合格の基準を数字で決める
「正しく答える」とだけ書いても、人によって解釈は違います。
そこで「何問中、何問できれば合格か」を具体的に決めます。
例:「FAQ100件をテストして、そのうち80件以上正しく答えられれば合格」
※合否の基準がはっきりするので、「まだ不十分」など主観で迷走しなくなる
2.利用者の声を数字にする
LLMは「正解かどうか」だけでなく「役に立つか」も重要です。
そこで利用者の評価を割合で表すようにします。
例:「テストユーザーの7割以上が『役に立った』と回答したら合格」
※技術者だけでなく実際の利用者の感覚を反映できる
3.ダメな基準も数字で決める
「誤情報が出たらダメ」とだけ書くと、ゼロを目指して終わらなくなります。
現実的には「多少の誤りは起こり得る」ので、どこまでなら許容するかを数字にします。
例:「テストで10件に1件までの誤答なら許容」
※現実的な落とし所が決まり、PoCを止めずに進められる
おさらい
- 合格ラインを数字で決める
- 利用者の感覚も数字で測る
- 許容できる失敗も数字で表す
👉 こうして「数字での約束事」を先に決めておけば、PoCの途中で「まだ足りない」「いや十分だ」と意見が割れることを防げます。
結果として、チームもクライアントも納得感を持って次のステップに進めます。
③PoCの目的を限定する|本番品質を求めない
PoC(概念実証)は「仮にやってみて、動くかどうかを確かめる実験」です。
ところが、ここで本番レベルの品質を求めてしまうと、必ず迷走します。
学びたいことを一つに絞る
良い例:「FAQで、よくある質問100件に対してどれくらい正しく答えられるかを確認する」
悪い例:「FAQの精度を確認しつつ、UIもデザインし、監視機能も入れて、ついでに多言語対応も試す」
👉 1つに絞ることで、結果が「できた/できなかった」で判断しやすくなります。
合格ラインを先に決める
「精度を上げろ」だけではいつ終わるかわかりません。数字で区切りをつけることが大事です。
良い例:「100件中80件以上が正解なら合格」
応用例:「テストユーザー10人中7人が『役に立った』と答えたら合格」
👉 数字で決めておけば、チーム内の主観が入り込まず、PoCを終わらせることができます。
期間を区切る
PoCはあくまで「短期で学びを得る実験」です。
期間を決めずに始めると、延々と改善し続けてしまいます。
良い例:「3週間で一区切り。結果が良ければ次のステップ、ダメなら撤退」
悪い例:「とりあえず精度が出るまでやり続ける」
👉 期間を切ることで「ここで判断する」と関係者全員が腹をくくれます。
おさらい
- やることは一つに絞る(最も確かめたいことだけ)
- 合格ラインを数値で決める(主観を排除できる)
- 期間を区切る(ダラダラ続けない)
これでPoCは「小さな実験」らしいシンプルな形になります。
逆に言えば、この3つが守れていないPoCは、ほぼ必ず迷走します。
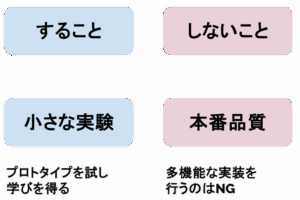
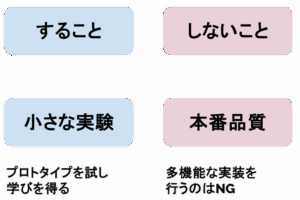
④コストをシナリオ単位で試算する|従量課金に備える
LLMは「使った分だけ課金」される仕組みです。
ところが、ざっくり「月10万円くらいでしょ」と見積もると、大体外れます。
よくある失敗
- 実際のユーザー数や利用回数を考慮せず、費用が想定の3倍以上に膨れ上がった
- デモでは数回しか使わなかったのに、本番では毎日数百回呼ばれ、一気に赤字化した
実務での工夫
- ユーザー数×利用回数×平均トークン数で試算する
- 例:「1日100人が平均5回利用、1回あたりの入力+出力が500トークン → 100×5×500=25万トークン/日」
- 単価を掛ければ、1日の想定コストが見える
- シナリオごとに分けて考える
- FAQ回答、文章要約、コードレビュー…シナリオごとに負荷が違う
- まとめて1本の数字で見積もらず、「シナリオ別の試算」を必ずする
- 早めに負荷テストする
- PoCのうちに「実際に100回呼んでみたらいくらになるか」を測っておく
- 感覚ではなく実データで語れるようにする
👉 「1ユーザー1日あたりいくら」まで落とし込むと、クライアントにも説明しやすくなります。
⑤運用改善サイクルを要件化する|作って終わりにしない
LLMはリリースしても「完璧な答え」を出し続けるわけではありません。
むしろ、誤答や表現のぶれが必ず残ります。
よくある失敗
- 改善の仕組みを用意せずリリース → 誤答報告が山のように溜まるだけ
- ユーザーの声を拾えず、「現場が困っているのに直せない」状態になる
実務での工夫
- ログを収集する
- ユーザーの質問とLLMの回答を必ず記録する
- 「どこで間違えたか」を後から分析できるようにしておく
- 改善の場を定期化する
- 例:「週1回レビュー会議を開き、誤答の代表事例を確認」
- 現場の声を拾い、改善優先度を決める
- 改善ループを仕組みに組み込む
- 「収集 → 分析 → 調整 → 再展開」を開発の要件に含めておく
- これがないと、改善が属人的で止まってしまう
👉 LLM開発は「リリース=完成」ではなく「リリース=改善の始まり」。
改善ループを要件として最初から設計に入れることが成功の鍵です。
LLM開発では「従来の要件定義のやり方」が通用しません。
揺らぎや曖昧さを前提に、出力条件の明確化・評価基準の数値化・PoCの目的限定・コスト試算・改善サイクルを仕組みとして要件に落とし込む必要があります。
この5つのチェックポイントを押さえれば、要件定義の迷走を防ぎ、PoCから本番運用までスムーズに進めることができます。
Skilligenceは、現場で成果を出すための研修・顧問・教材を提供する実務支援ブランドです。
・研修:要件定義・業務設計・LLM活用などを体系的に学べる実践講座
・顧問:プロジェクト進行や開発体制の課題を継続的にサポート
・教材:独学でも現場スキルを身につけられる学習コンテンツ
実務で使える知識と仕組みづくりを、学びから伴走まで一貫して支援しています。
▶ IT顧問サービスを見る
▶ 研修一覧を見る
▶ 教材一覧を見る(Starter・Advanced公開中)