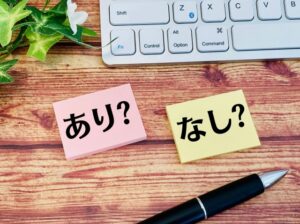この画面なんですが、なんだかデザインが指示したものと違っていて…。特に変更のお願いはしていないんですけど…



…なるほど、これ、おそらく“気を利かせて変更された”ケースかもしれませんね。オフショア開発では、よくあることなんですよ。



そうなんですね…。でも、こちらとしては困りますよね、勝手に変えられてしまうと。



ごもっともです。ただ、向こうのエンジニアからすると、“そのほうが使いやすいと思った”とか“親切のつもりだった”ということもあって。悪意があるわけではないんですよ。だからこそ、最初にしっかりルールや方針を共有しておくことが大事なんです。
はじめに
オフショア開発の現場では、「仕様通りに作ってくれる」と思っていたのに、「なんか勝手に変わってる…」という現象に出会うことがあります。
一見すると“ミス”や“手抜き”に見えるかもしれませんが、実は多くの場合、「よりよくしようとした」善意の判断であることも少なくありません。
本記事では、この「勝手な変更」が起きる背景とその対策**を紹介します。
なぜ勝手な変更が起こるのか?|背景にある“ズレた親切心”
オフショア側のエンジニアが仕様に手を加えるのは、単なる怠慢ではありません。
「より良いと思ったから」「このままだとユーザーに不親切だと思った」など、善意からの判断であることも。
その背景には、文化・業務プロセス・判断基準の違いがあります。
実例1:ボタンの色や配置が指示と違っていた
●内容
デザインカンプでは「送信ボタンは青、左寄せ」と指定していたが、納品された画面では「緑色、中央寄せ」になっていた。
●理由
- 現地エンジニアが「緑のほうが“進む”という意味で直感的だ」と判断
- スマホユーザーが多い地域では中央寄せが使いやすいという現地基準があった
- 「UXを良くするための改善」として自主的に変更されたが、日本側と“完成の定義”が違っていた
実例2:想定外のバリデーションが追加されていた
●内容
入力フォームに、依頼していない独自のエラーチェック(たとえば特殊文字の除外)が追加されていた。
結果として、一部のユーザーが入力できない状態に。
●理由
- 「セキュリティ強化になる」と判断して現地の過去経験ベースで追加
- オフショア先では「柔軟に改善することが求められる」と評価される文化があり、
仕様にないものも“良かれと思って”実装した - 日本側では「仕様通りに忠実に作ることが正しい」と認識されていたため、齟齬が発生
実例3:内部処理のロジックが仕様書と異なる実装に
●内容
「一覧表示の順番は登録日時の降順」と指定したにも関わらず、納品物ではステータス順→登録日時の二段階ソートが適用されていた。
●理由
- 開発側が「このほうが業務に使いやすいのでは」と判断して仕様を“改善”したつもり
- 現地では要件が曖昧な場合、「ユーザーにとってベターな仕様を考えることが良い」とされることがある
- 仕様の“背景意図”が共有されていなかったため、判断を任された形になっていた
なぜこういった“勝手な変更”が発生するのか?
共通して見られる背景は以下の通りです。
文化的価値観の違い
「自分で考えて改善する」ことが評価される文化では、
仕様通りに作るだけでなく、より良くなると思った点は積極的に変えることが正しいとされる傾向があります。
日本では“仕様厳守”が重視されがちなので、ここに認識のギャップが生まれます。
指示の明確さ不足
「ここまで実装してほしい」「これは絶対に変更しないでください」といった明確な指示がない場合、
開発者側が自由に判断してしまうことがあります。とくに仕様書に曖昧な表現があると、“補完”されてしまうことも。
仕様の意図・背景の共有不足
「なぜこの仕様なのか」という背景情報を共有していないと、開発者が“仕様=参考情報”と解釈し、目的に沿う別の方法を選んでしまうことがあります。
特にUIや業務ロジックでは、目的の理解の有無が行動を大きく左右します。
トラブルを防ぐ3つの具体的対策
対策1:「やってはいけないこと」も仕様に明記する
オフショア開発では、**「書いていない=やってもよい」**と判断されるケースが少なくありません。そのため、「この処理は変更しないでほしい」「この画面のデザインは絶対に守ってほしい」といった禁止事項や絶対条件も明確に記載することが重要です。
言葉だけではなく、モックアップやスクリーンショットを添付することで視覚的に認識を揃えることも有効です。
対策2:「提案は歓迎、変更は事前相談」のルールを徹底する
文化的に“よかれと思って改良する”傾向がある場合、それを完全に抑えるのではなく「提案は歓迎、ただし実施は事前承認」というルールにすることで、改善の意欲を活かしながら統制を取ることができます。
「仕様と違っていたら即NG」ではなく、「提案してくれたことには感謝、でも最終判断はこちらがする」というスタンスで進めると信頼関係も築きやすくなります。
そのルールは、キックオフ時や日々のコミュニケーションの中で繰り返し伝えることが大切です。
対策3:「仕様の背景や目的」を定期的に共有する
仕様そのものだけでなく、「なぜそうするのか」という背景情報を伝えることで、開発者側が意図を汲んで判断しやすくなります。
例えば「この画面のデザインは、ユーザーの誤操作を防ぐためにボタンを左寄せにしています」など、目的を説明するだけで勝手なアレンジは格段に減ります。
また、週次ミーティングや進捗報告の際に、仕様の理解度を確認する場を設けるのも効果的です。
「気軽に確認していいんだ」という雰囲気を作ることで、すれ違いの芽を早期に摘むことができます。
オフショア開発で「そんなの頼んでない…!」という仕様変更に遭遇すると、驚きや困惑とともに、つい相手に対する不信感が芽生えてしまうかもしれません。
しかし、その多くは**悪意ではなく“ズレた親切心”や“文化の違い”**からくるものです。
だからこそ必要なのは、人を責めることではなく、ズレを前提とした仕組みを整えること。
- 「やってはいけないこと」まで仕様に明記する
- 「提案はOK、実行は事前相談」というルールを明確にする
- 仕様の背景や目的をしっかり共有する
これらの積み重ねによって、信頼関係を保ちながら品質と再現性のある開発体制が作られていきます。
文化も価値観も違うからこそ、共通のルールと認識のすり合わせが何より大切。
“仕様通りに作ってもらうための仕組み”を、あなたのチームにもぜひ取り入れてみてください。
Skilligenceは、現場で成果を出すための研修・顧問・教材を提供する実務支援ブランドです。
・研修:要件定義・業務設計・LLM活用などを体系的に学べる実践講座
・顧問:プロジェクト進行や開発体制の課題を継続的にサポート
・教材:独学でも現場スキルを身につけられる学習コンテンツ
実務で使える知識と仕組みづくりを、学びから伴走まで一貫して支援しています。
▶ IT顧問サービスを見る
▶ 研修一覧を見る
▶ 教材一覧を見る(Starter・Advanced公開中)